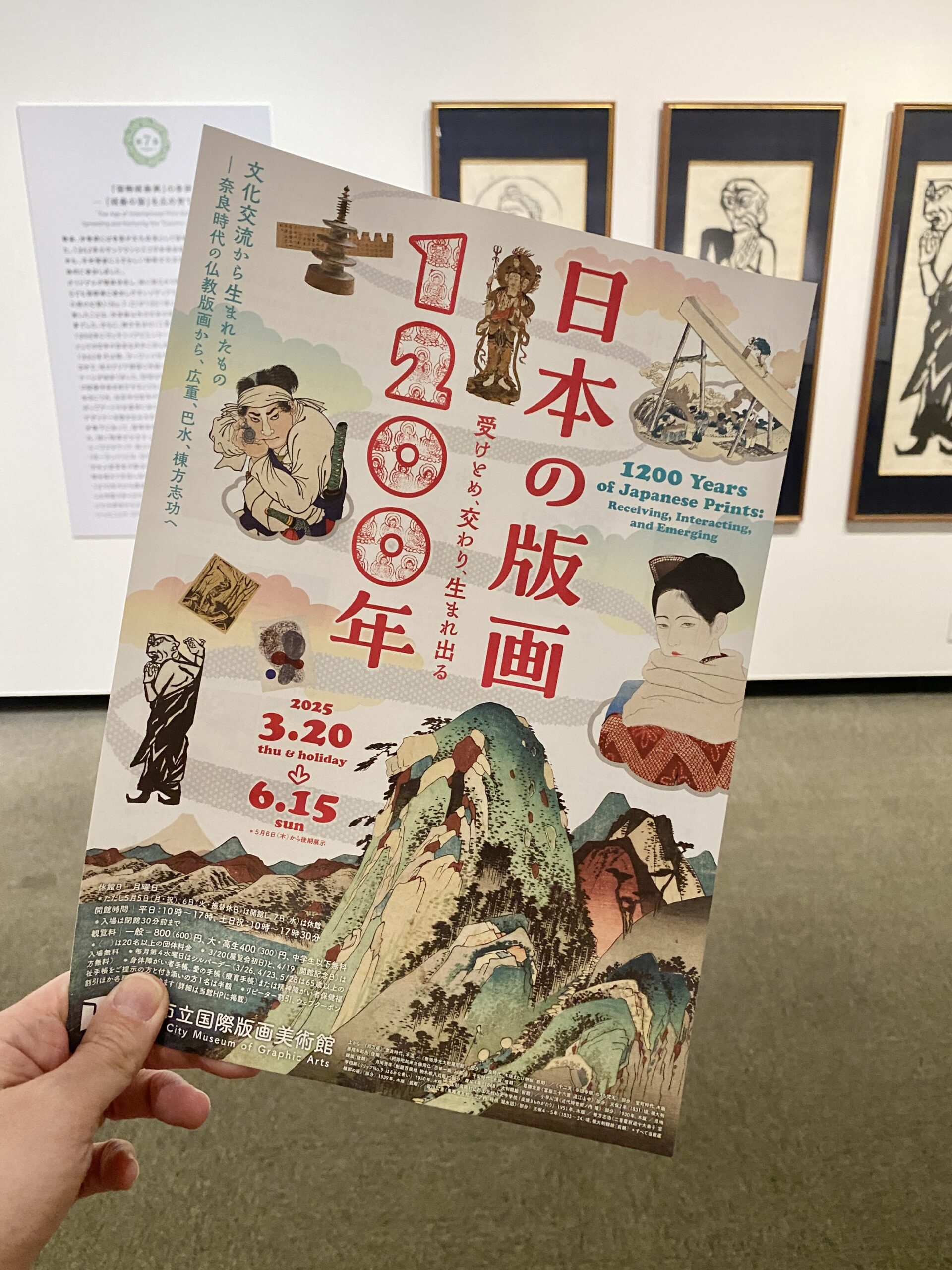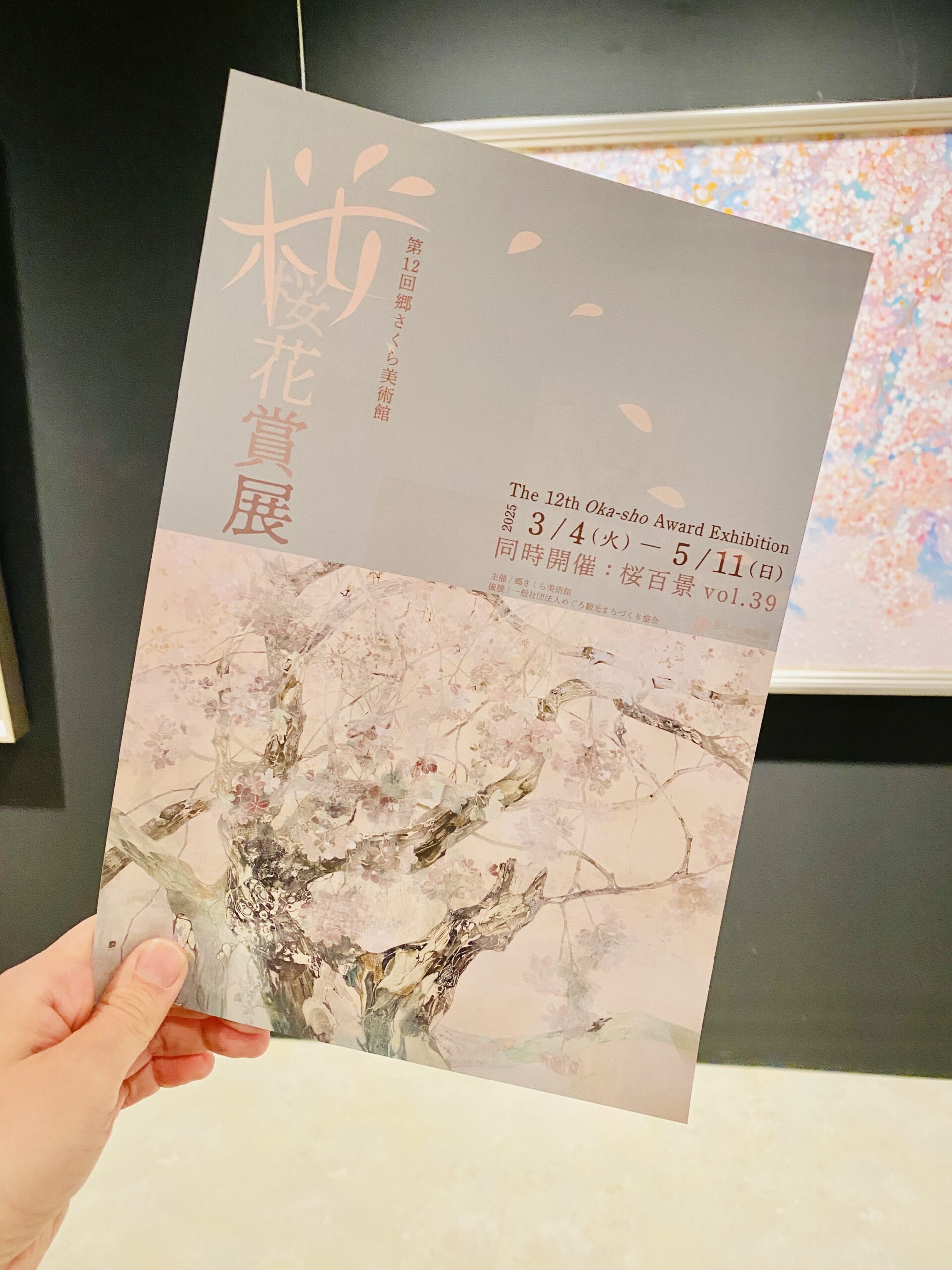[着物でお出かけ] 蒔絵を通して歴史を学ぶ「大蒔絵展」
今回は、東京・日本橋にある三井記念美術館で開催中の「大蒔絵展」へ。 「蒔絵」とは、漆器に漆で絵や文様・文字などを描き、漆が固まらないうちに蒔絵粉(金や銀の粉)を蒔いて装飾を付ける技法です。
「蒔絵」とは、漆器に漆で絵や文様・文字などを描き、漆が固まらないうちに蒔絵粉(金や銀の粉)を蒔いて装飾を付ける技法です。
展示作品は平安時代から近代までのものが100点以上。作品が時代ごとに展示され、歴史と重ねながら楽しめます。 ※こちらは撮影OKだった作品
※こちらは撮影OKだった作品
展示は平安時代の「源氏物語絵巻」や「法華経」から始まり、文字の美しさや綺麗さに感動させられます。
鎌倉時代は、蒔絵粉を作る技術が向上して新たな技法が生まれ、室町時代にはさらに高度な技術を多用した複雑な装飾に発展します。箱の中や蓋の裏までも蒔絵が施された作品は、箱の持ち手や留め具だけでもジュエリーになりそうなくらいの繊細さで、専門的な知識がなくても、技術の素晴らしさが感じ取れます。
豊臣秀吉が天下統一を果たした桃山時代には、日本を訪れるようになったキリスト教の宣教師や商人たちが、日本の蒔絵に魅了され、家具や祭礼具などを注文し持ち帰っていました。キリストが蒔絵で描かれていたり、日本語ではなく「IHS」とアルファベットが書かれているのも新鮮です。
「南蛮屏風」には当時の貿易の様子が描かれ、南蛮人の服の柄が和風だったりするのを発見すると、面白くて嬉しくもあります。江戸時代は鎖国のイメージがありますが、中国とオランダとは貿易をしていたので、オランダ東インド会社を経由して、遠く離れた国まで輸出されたものもありました。展示の中で一番印象に残ったのは、イスラム圏へ輸出されていた「水差し」。細くて長い注ぎ口がついたイスラム独特のシルエットとの斬新なコラボレーションに驚きました。
明治維新後は時代の流れによって職人たちも減ってしまいましたが、昭和25年に文化財保護法が制定され、人間国宝の方々を中心に、現代に至るまで技術の保存や伝承がなされています。 千年以上続く伝統技法に魅せられて豊かな時間を過ごせました。
千年以上続く伝統技法に魅せられて豊かな時間を過ごせました。
着ていた着物の色のように心もスッキリ☆お時間があればぜひ行ってみてください。
ーーーーーーー
三井記念美術館
東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階
東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前駅」A7出口より徒歩1分
「大蒔絵展」漆と金の千年物語
開催期間:2022.10.1(土)〜2022.11.13(日)