文様図鑑 vol.22 江戸小紋3役
美しい自然を切り取った文様に、幸せを願う吉祥紋、時にはダジャレを効かせた洒落紋など、着物には数え切れないほどたくさんの文様を見つけることができます。
デザイン性の高さはもちろんのこと、その文様に込められた意味を知ると着物はもっと面白くなるはず!「文様図鑑」では毎回、着物や帯から素敵な文様を紹介します。
今回は、藩の定め柄を模様にした裃(かみしも)が作られるようになったことが、始まりの江戸小紋。その中でも格の高い3役です。
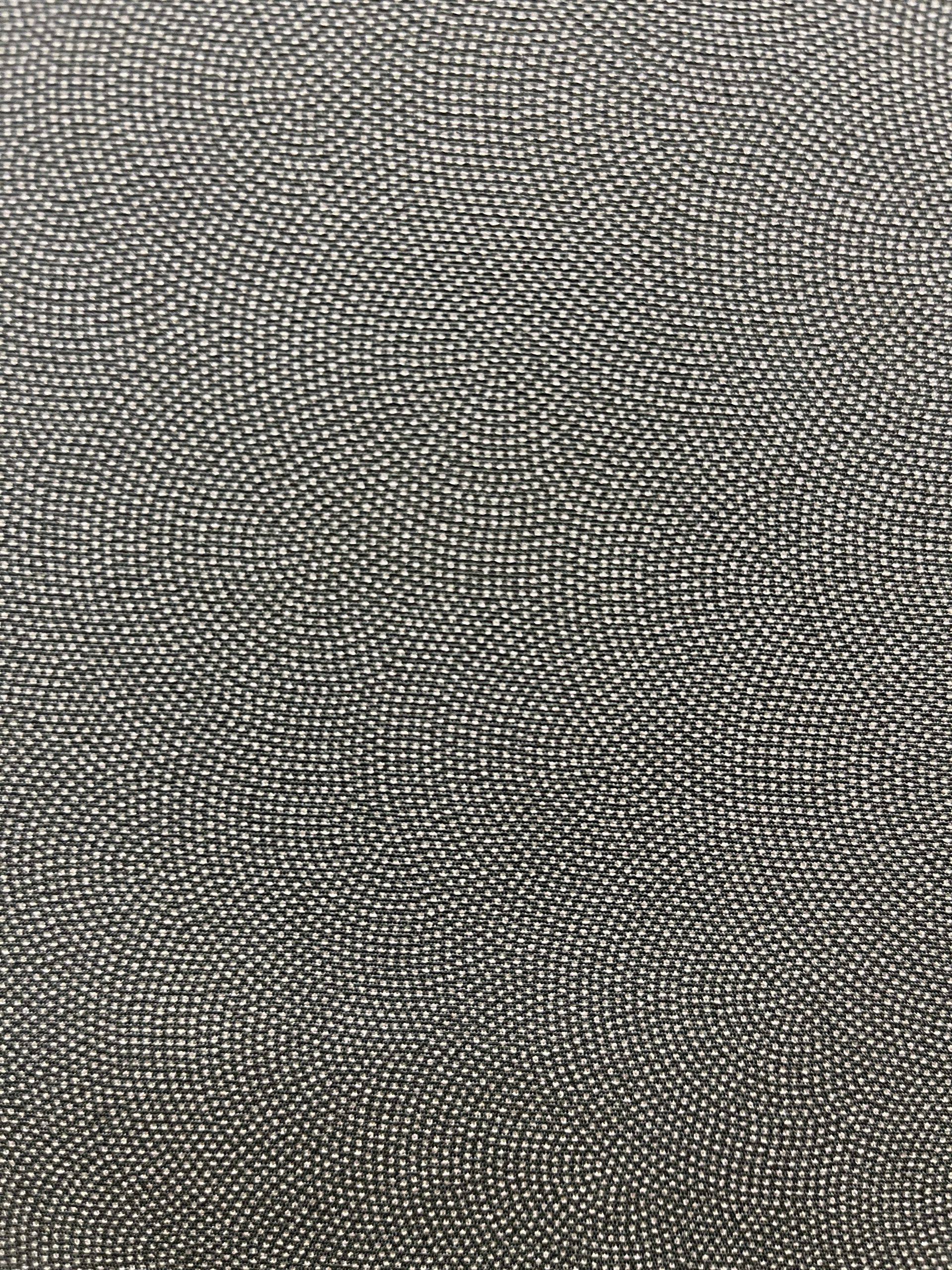
※写真は鮫小紋
江戸小紋は昔、武士達が柄の華やかさを競っていましたが、幕府の規制が入り華やかさを抑えられるようになったことで柄を細かくすることが現在の柄に繋がっていると言われています。
江戸小紋と呼ばれるようになったのは意外と遅く
昭和29年から細かく規則正しくびっしり配列され、一見無地に見える小紋柄を他の小紋と区別して、「江戸小紋」と呼ぶようになりました。
その中で「鮫」「行儀」「通し」の3つが江戸小紋3役と呼ばれています。
「鮫」
細かい点を鮫の皮状に並べられている柄。特に細かいものを極鮫といい、極鮫顧問は
紀州徳川家の定め小紋になっています。

※写真は通し小紋
「通し」
細かい点が縦横に整然と並んでいる柄を通し柄と言い、
点が四角形になっているものを角通しと言います。
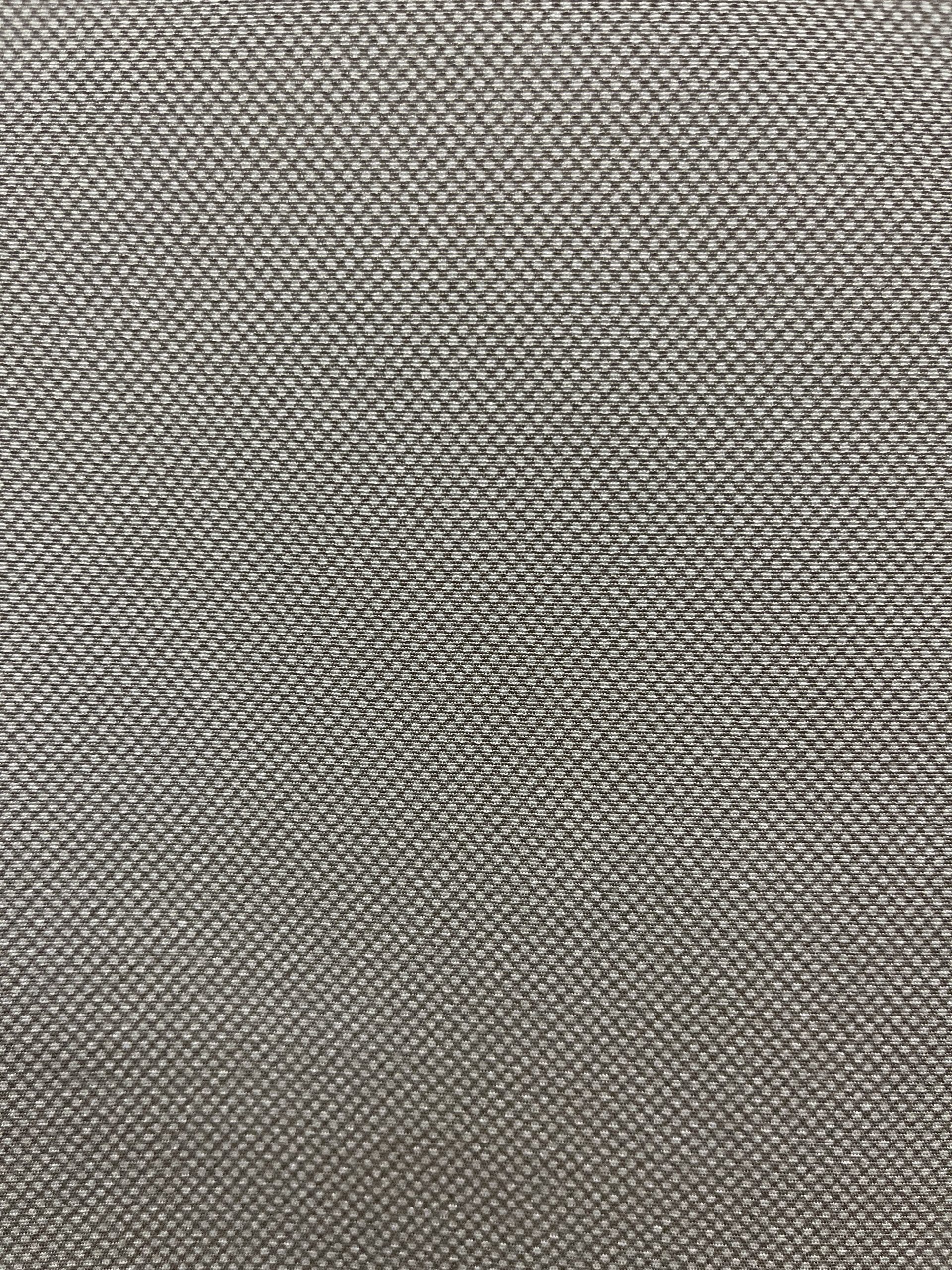
※写真は行儀小紋
「行儀」
通しと若干の違いがあり、細かい点が斜めに並んでいるものを行儀と言います。










