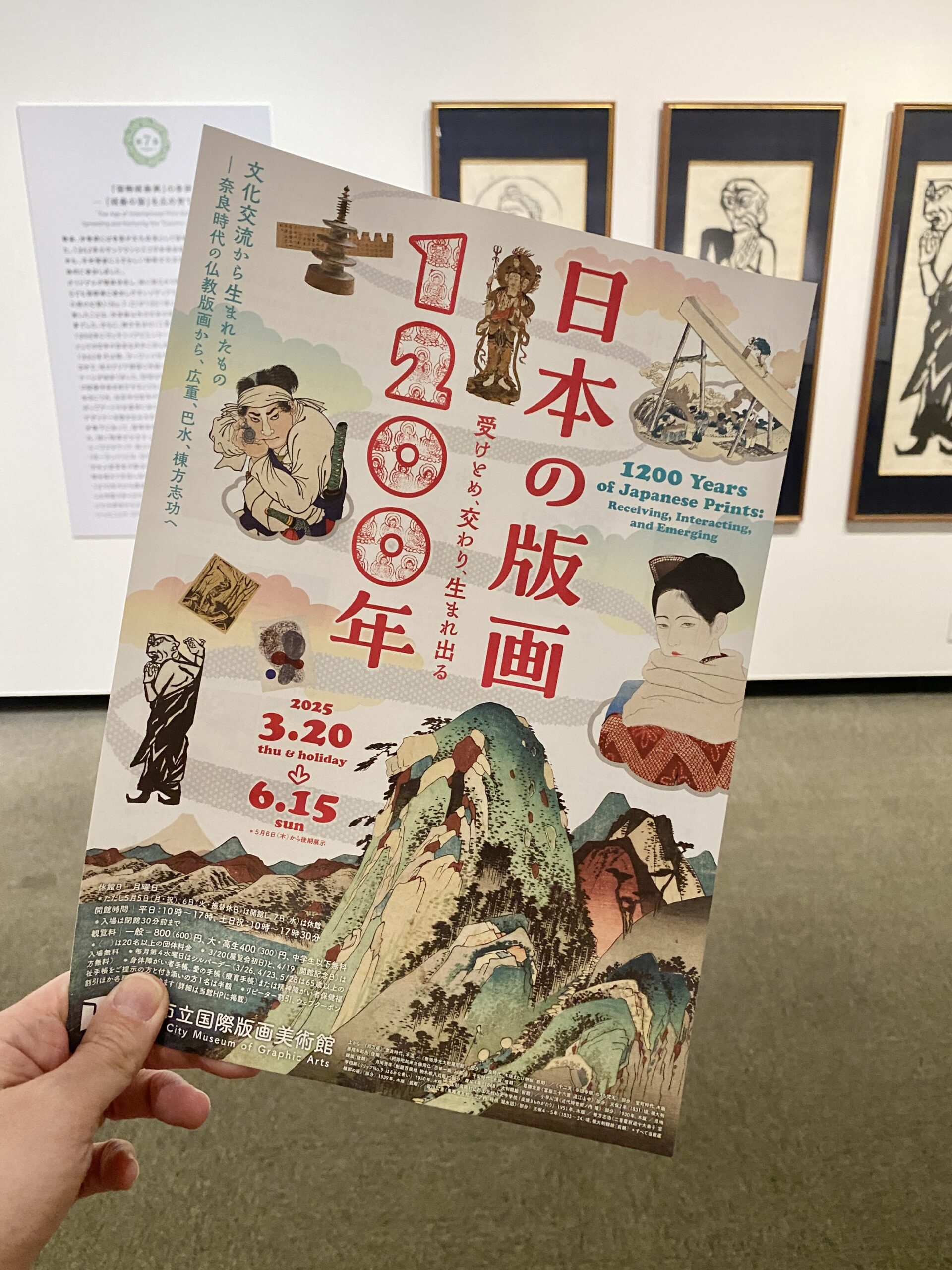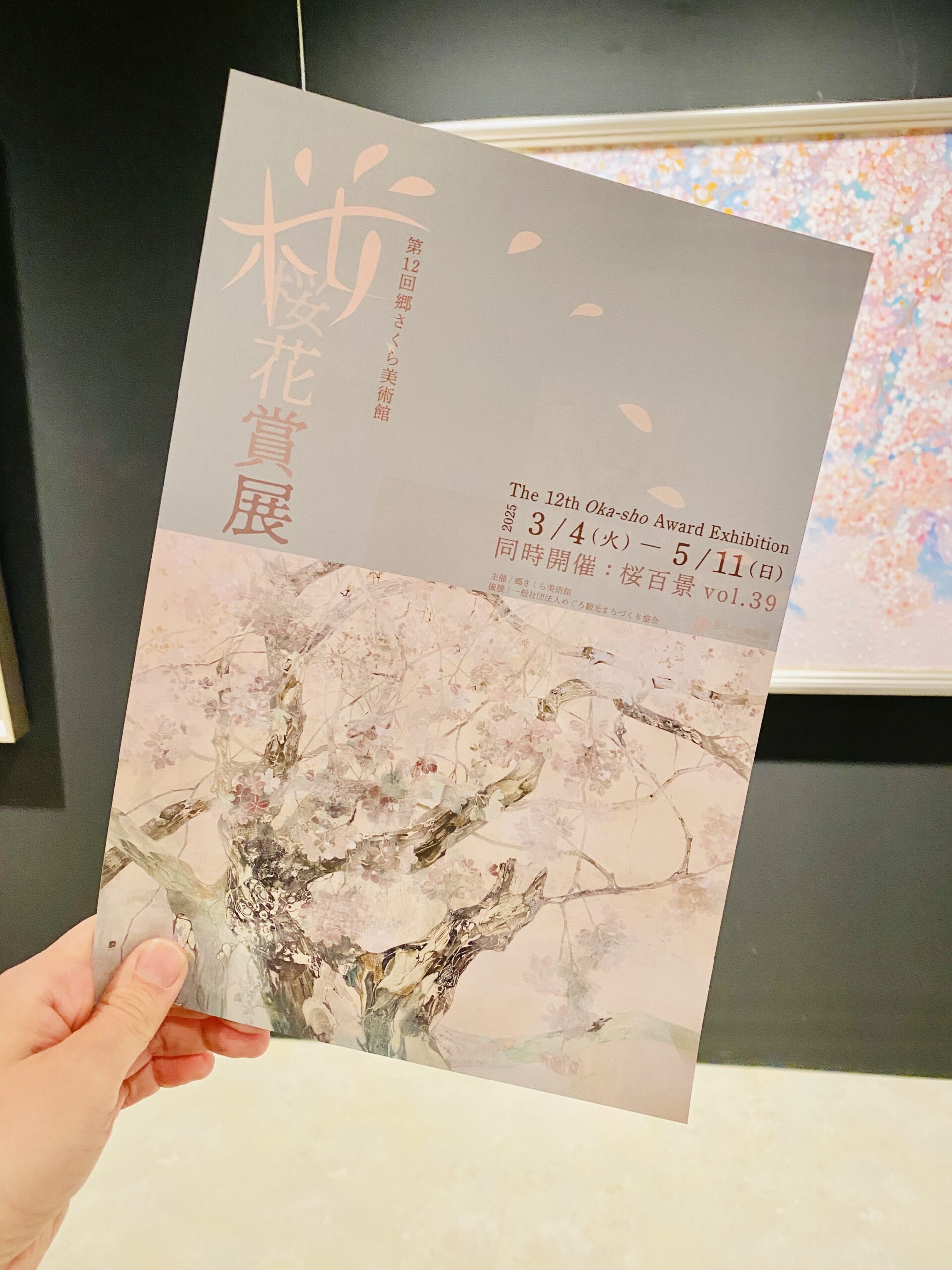【群馬県・富岡製糸場】養蚕だけじゃない!日本初の官営模範工場で学ぶ。前編

<富岡製糸場>は2014年6月に日本で18件目の世界遺産として正式登録されました。「富岡製糸場と絹産業遺産群」として周辺に点在する養蚕(ようさん)関連の文化財を含めての登録。
絹産業の技術革新に大きく貢献し、いまや日本だけでなく世界的に見ても大変貴重な遺産となりました。
群馬県を訪れた際は絶対に外せない、一生に一度は行きたいスポット!
解説員の方にお話を伺いながら見学させていただきました。
とても広く見応えたっぷりの施設内を前編・後編に分けてご紹介したいと思います!
【目次】
1.<富岡製糸場>が誕生した理由とは
2.生き血を取られる⁉︎ 工女の待遇は?
3.国宝に指定された3つの建物
-----------------------------------------------------------------------
1.<富岡製糸場>が誕生した理由とは
◆いつ、誰により建てられたのか?
1872年(明治5年)に日本で最初の官営模範工場として操業開始した<富岡製糸場>。
明治政府が質の良い生糸を大量生産できる「器械製糸技術」を国内に広めるために設立した工場です。
1987年(昭和62年)3月の操業停止まで115年間、休むことなく製糸工場として稼働し続けました。

◆なぜ国が立ち上がり模範製糸工場を建てたのか?
外国との交流が限定的だった日本ですが黒船来航により1859年、3つの港「函館・横浜・長崎」が開港し貿易が始まります。
翌年、蚕(かいこ)の卵や生糸が日本の輸出量の大半を占めました。
その理由として、ヨーロッパで蚕の病気が流行り生産が激減していたこと。
他にも生糸の大量輸出国である当時の中国がアヘン戦争などの国内の混乱により生産が激減していた、そういった背景から日本の生糸の輸出は始まったのです。
生糸は貿易の上で需要が高く、また外貨獲得のために大変重要な輸出品でした。
しかし当時はまだ手作業で生糸を作っていたため、外国からの大量注文に追い付けない状況でした。
なかには質の悪い生糸を質の良い生糸に混ぜて売る人も出てきたことにより、日本の生糸の評判が下がり問題になりました。
明治維新を迎えた日本に対し、諸外国は改善の要望書を提出いたします。
明治政府は問題を解決し、質の良い生糸をたくさん作るため、また貿易を盛んにするためにヨーロッパの器械製糸の技術を取り入れることにしたのです。
さらに器械製糸場の普及を図るために明治政府による工場建設が決められました。
<富岡製糸場>は政府によって初めて建てられた製糸工場なんです。

◆建設場所に群馬県富岡市が選ばれた理由は?
日本初の官営模範製糸場ですがなぜ群馬県だったのか、疑問に思いますよね。
明治政府は製糸場を建設するため、地元で養蚕が盛んだった3県、長野県・埼玉県・群馬県を候補地に挙げました。
ではなぜ他の2県も養蚕が盛んだったにもかかわらず、群馬県富岡市に決定したのでしょうか。
理由は5つあります。
①養蚕が盛んで、原料繭が確保できたこと
②工場建設のための広い敷地が確保できたこと
③既存の用水路を使うことで水の確保ができたこと
④燃料である石炭が近くから採れたこと
⑤外国人指導による工場建設に地元住民が同意したこと
この5つの条件をクリアしたため、群馬県富岡市が選ばれました。
その後<富岡製糸場>をモデルに、全国に製糸場建設が進められていくこととなります。
-----------------------------------------------------------------------
2.生き血を取られる⁉︎ 工女の待遇は?
明治政府は工場が完成に近づいた時、日本全国に工女の募集を行いましたがなかなか集まりませんでした。
それは<富岡製糸場>に入ると「外国人に生き血を取られる」という噂が流れたからでした。
当時日本では色のついた飲み物が珍しかったようで、ワインを見た人が勘違いをしたそうです。
そこで政府は工女を募集する理由をしっかりと説明し、フランス人が飲んでいるのは「血」ではないことを国民に伝えました。
また初代製糸場長の尾高惇忠氏は娘である、勇さん14歳を工女第一号として入場させて範を示しました。
こうして、当初の予定であった7月より遅れて10月4日から操業が開始されたのです。
ここで働いていた工女は、全国から集められた15歳から30歳位の方で年齢の幅は広かったそうです。
工女と聞くと「倒れるまで働かされていた」など可哀相なイメージを持つ方もいるそうですが、<富岡製糸場>ではそんなことはありませんでした。
場内に診療所・病室が設けられており、従業員の全員が医療の提供を受けることができました。

工女の労働時間も創業当初は1日7時間45分と定められていました。
朝は7時から夕方の17時まで。朝と昼に1時間と15時から15分の休憩がありました。
また当時は電気がなかったこともあり、労働時間が定められながらも暗くなると作業ができないので、勤務時間の調整はされていたそうです。
明治時代の頃から福利厚生がここまで考えられていたことに驚きませんか。
-----------------------------------------------------------------------
3.国宝に指定された3つの建物
<富岡製糸場>が建てられてから約150年が経ちますが、とても良い状態で保存されています。
国宝や重要文化財に指定されている建物が多くあり見応えたっぷりです。
建物・施設内をご紹介したいと思います。
世界遺産に登録された同じ年の12月、東置繭所(ひがしおきまゆじょ)・西置繭所(にしおきまゆじょ)・繰糸所(そうしじょ)の3つの建物が国宝に指定されました。
まず正面入口から入ると目の前に見える建物、こちらが東置繭所です。

画像提供:富岡市
建物は木材で骨組みを造り、壁に煉瓦を用いた「木骨煉瓦造(もっこつれんがぞう)」という西洋から来た建築技術が採用されています。
アーチの部分を固定するために石がはめ込まれていますが、これを「キーストーン」というそうで、建設された年号が掘られています。

画像提供:富岡市
そしてこちらが西置繭所です。

離れて撮影しても入りきらないほどの広さ!
長さは104.4メートルあるそうです。
東置繭所と西置繭所の2階で乾燥させた繭を貯蔵していました。
当時は一年に一度しか養蚕が行われていなかったので、一年間に使う繭をまとめて買い入れしていたそうです。
そのために広い置繭所があるのですが、東置繭所では乾燥させた繭を約32トンも保管できたそうです。
そして3つ目の国宝、繰糸所です。

繰糸所は長さ140.4メートルと<富岡製糸場>の中で一番大きな建物です。
こちらで繭から生糸をとる作業が行われていました。
外から見た大きな特徴は、屋根の上に小さな屋根が乗っている点です。これを「越屋根」というそうです。
中ではたくさんのお湯を使って繭から糸を取り出すのですが、蒸気がたくさん出るので換気のために設置されています。
そしてもう一つの特徴はガラス窓がたくさんあることです。
明治時代は電灯が無かったため、外からの光をたくさん取り入れる必要があったんです。

創業当初はフランス式の繰糸器300釜が設置され、世界最大規模の製糸工場でした。
小屋組には「トラス構造」という従来の日本にない建築工法を用いています。
そのため、建物内部は中央に柱のない広い空間が保たれています。
現在展示されているのは1966年(昭和41年)以降に設置された自動繰糸機です。
-----------------------------------------------------------------------
いかがでしたか?
前編では、世界遺産である<富岡製糸場>誕生の理由と国宝に指定されている3つの建物のご紹介でした。
西置繭所は6年間の工事を経て2020年にグランドオープンしたそうで、建物の特徴が生かされた展示やライトアップが圧巻です!
後編ではそちらも含め、たっぷりとご紹介していきます。
ぜひご覧ください!

----------------------------------------
富岡製糸場
●住所:群馬県富岡市富岡1-1
●電話(場内総合案内所):0274-67-0075
●開場時間:9:00〜17:00(最終入場16:30まで)
●休場日:年末(12月29日〜12月31日)
●見学料:大人 1,000円/高校・大学生(要学生証) 250円/小・中学生 150円
●オプション料金:ガイドツアー参加(解説員による解説) 大人 200円/中学生以下 100円
●団体オプション料金:解説員 1名あたり 3,000円
●HP:http://www.tomioka-silk.jp/tomioka-silk-mill/
-----------------------------------------------------------------------
撮影協力:富岡市・富岡製糸場
※いずれも消費税込み
※データは2021年11月時点での情報です。
最新の情報は施設にお問い合わせください。
▼STAFF
モデル:桜井 あやこ(アウグストゥス)
撮影:岩嵜一真
取材・文:キモノプラス編集部