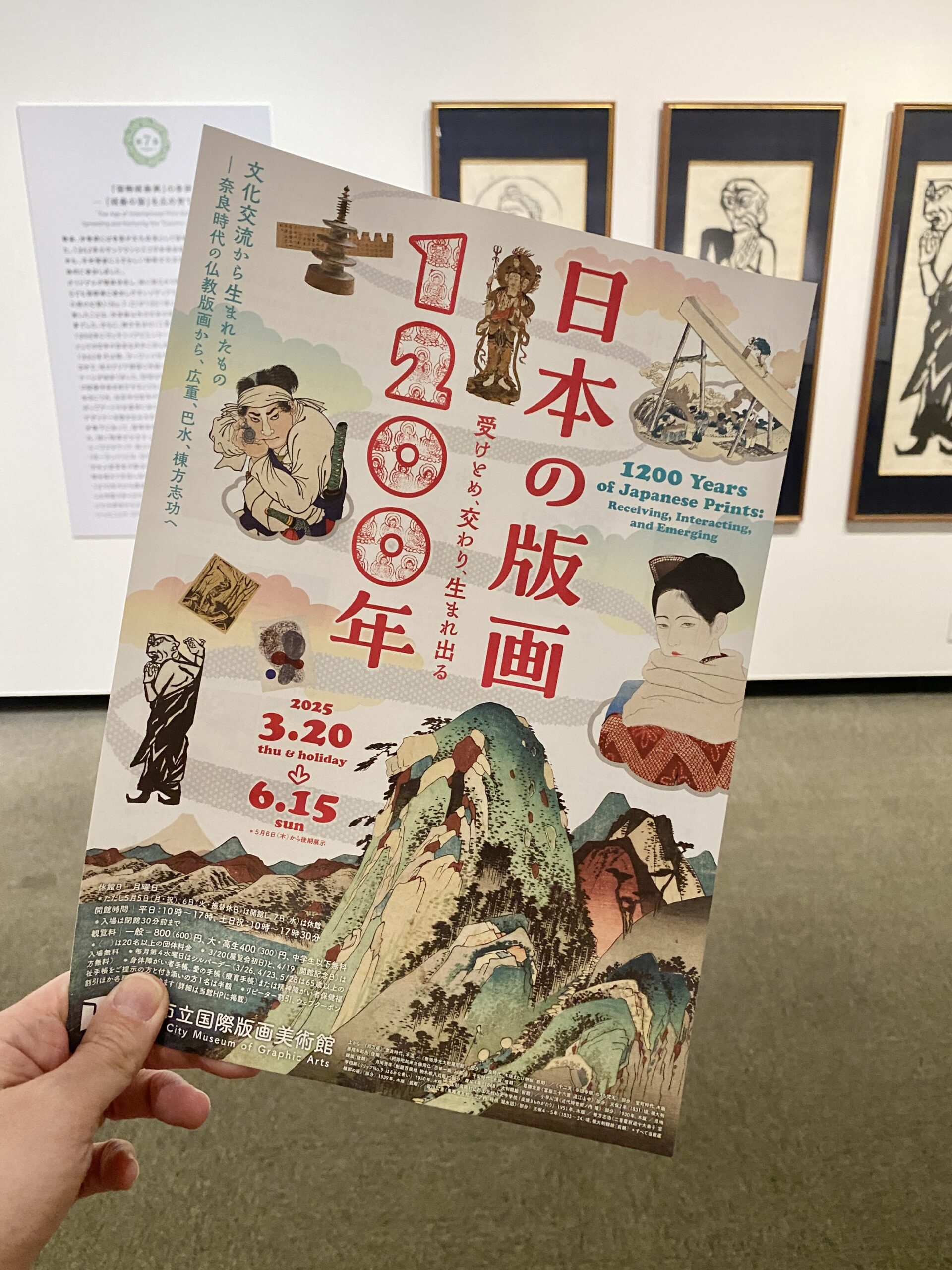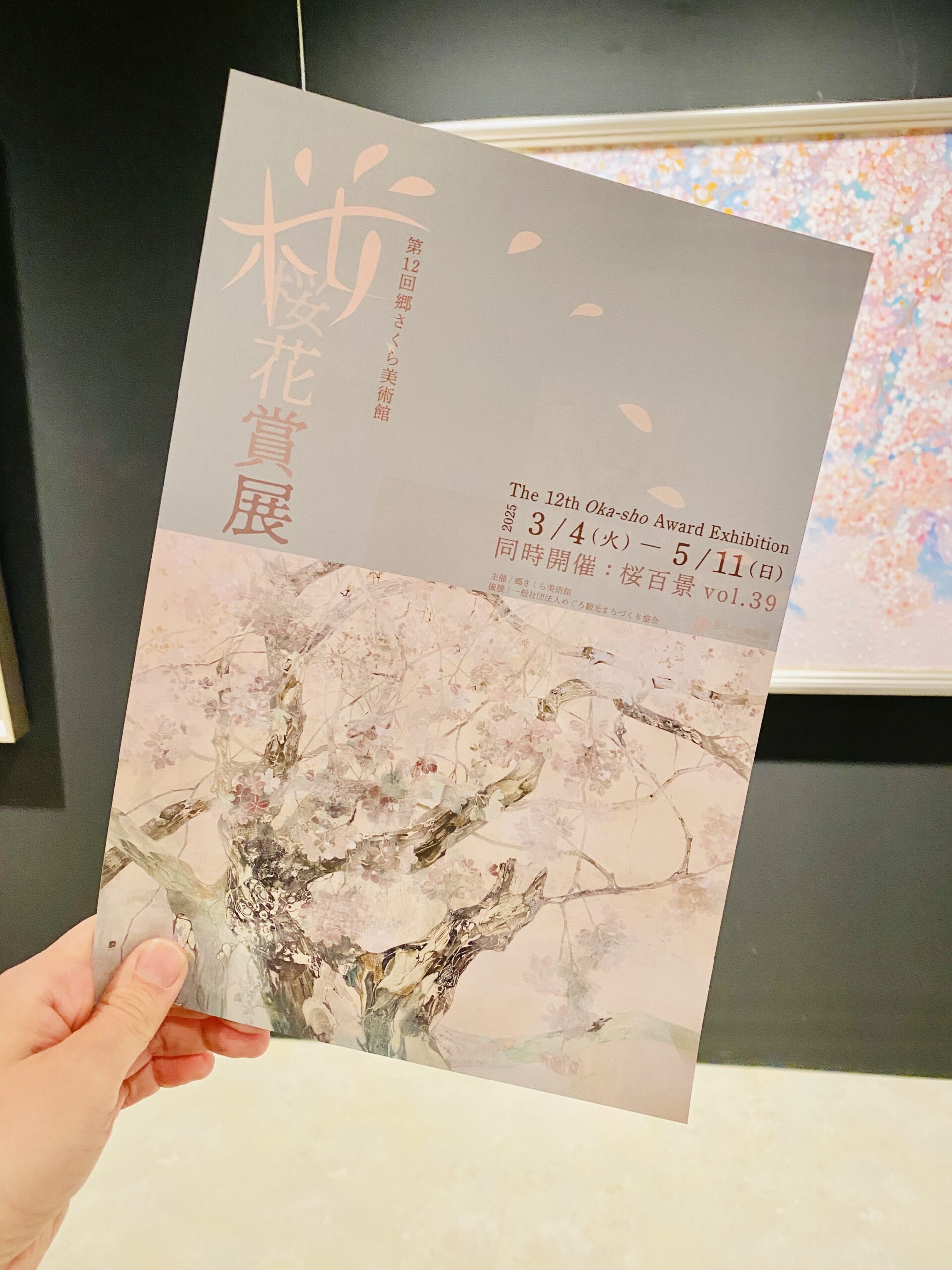【埼玉県・ちちぶ銘仙館】アンティーク着物で大人気!秩父銘仙とは?

最近はレンタルでアンティーク調の着物を選ぶ方がとても増えていますね!
「銘仙(めいせん)」はアンティーク着物の代名詞ともいえる存在で、大正から昭和初期にかけて日本中で流行した絹織物です。
当時は銀座を歩く人の2人に1人が銘仙を着ていたというほど流行していました。
栃木県足利市、群馬県桐生市・伊勢崎市、埼玉県秩父市、東京都八王子市の5ヶ所が五大産地とされており、それぞれに特徴があります。
今回は<ちちぶ銘仙館>にお邪魔し「秩父銘仙」について教えていただきました!
【目次】
1.ブームの火付け役はお嬢様だった!?
2.銘仙の始まりは◯◯◯だった!
3.<ちちぶ銘仙館>で出来る貴重な体験
4.「ふじや衣裳」で着物をレンタル
-----------------------------------------------------------------------
1.ブームの火付け役はお嬢様だった!?
「銘仙(めいせん)」とは絹の平織物の総称です。
着物と聞くとかしこまったイメージがあると思いますが、庶民が初めておしゃれできる様になったきっかけが「銘仙」といわれています。
ブームの火付け役は学習院に通う「お嬢様」でした。
当時 豪華な振袖を着て学習院に通っていた女学生たちをみて、学院長だった乃木希典(のぎ まれすけ)は「華美な格好で来てはいけない」と言い渡します。
それでも可愛い着物を着たいお嬢様たち。
そこで商人・機屋が共同で色鮮やかで多彩な柄の可愛い着物を生み出しました。
これが女学生たちのニーズと合致して大流行となり、幅広い年齢層の女性に支持されることとなりました。そして普段着として、またお洒落着として日本全国に普及していったのです。

銀座を歩く人の2人に1人が着ていたという銘仙は、この辺りで作られたものだそうです。
産地が5ヶ所あり、それぞれに特徴があります。
秩父銘仙は「ほぐし捺染(なっせん)」という技法を用いて織られている、という特徴があります。
分かりやすくいうと経糸(たていと)にだけ型染めをし、1色の緯糸(よこいと)と織っていく、というものです。
その緯糸の色を変えるだけで色違いを創ることができます。
染めの着物というのは白い生地に職人が何ヶ月もかけて絵描きますが、型染めは早く染めることができるので時間をかけずに創ることができます。
そういった点も大流行した理由の一つなのでしょう。今でいうファストファッションの様な存在だったようです。
秩父銘仙の最盛期であった大正ロマン・昭和モダンの頃は年間に約200万着も生産されていました。

そして秩父銘仙のもう一つの特徴が「玉虫色」ということです。
見る角度によって色味が変わるので色んな表情が楽しめます。
この機織の周りを180度歩いてみると色味が場所により変わって見えます。

大正の終わりから昭和にかけて科学染料が手に入る様になったため色数が増えましたが、それまで庶民は黒・白・茶などの地味な色の着物を着ていました。
柄物の着物を着ることなどなく、ましてや絹なんて、、という時代です。
銘仙の技法が生み出され、庶民が初めて手にできる「華やかな柄物の着物」の誕生に女性たちはさぞ喜んだことでしょう。
-----------------------------------------------------------------------
2.銘仙の始まりは◯◯◯だった!
銘仙の定義は「絹である」そして「先染めで平織りである」ということです。
秩父は昔から養蚕(ようさん)が盛んでした。
明治の頃に政府が養蚕をすすめており、良い繭・良い糸は売られていきました。
その過程でどうしても「クズ繭」ができるので、自分達用に糸を紡いで染めて織り、着ていたそうです。
それがそもそもの銘仙の始まりでした。

<ちちぶ銘仙館>には「糸繰室(いとくりしつ)」があります。
こちらで繭を乾燥させて煮て、数個の繭から一本の生糸にしていきます。
月に一回、第二土曜日には繭から糸を採っているそうです。
-----------------------------------------------------------------------
3.<ちちぶ銘仙館>で出来る貴重な体験
<ちちぶ銘仙館>がオープンしたのは2002年(平成14年)ですが、こちらの建物自体は昭和5年に建てられたものだそうです。
当時は繊維工業試験場の秩父支部として使用されていました。
のこぎり屋根になっているのが織物工場の象徴です。

これは北側から季節関係なく一定の光を取り入れられるように考えられた設計だそうです。
中に入るとまだ使われている現役の機械があります。
左にあるのが経糸を並べる機械「整経機(せいけいき)」
右にあるのが糸に撚りをかける「撚糸機(ねんしき)」です。


糸をボビンに巻く機械
<ちちぶ銘仙館>では埼玉県の支援により秩父銘仙の「後継者育成講座」というものがあります。
生徒さんは3年間、土曜日に通い自分の作品を織っているそうです。
こちらは見学もできます!館内には機織りの音がリズム良く響きます。

「後継者育成講座」は毎週通うものですが、それとは別にたくさんの体験ができるのがこちらの魅力です。
伺った時は和紙に型染めをし、行燈(あんどん)を作る体験が行われていました。

和紙の上に型紙を置き、染料を乗せて染めます。
色を変えるときは型紙・染料を変え、染め重ねていきます。
あと人気の体験はコースター作りだそうです。

奥にたくさんあるカラフルな糸から好きな色を選び、手前の織機でコースターを織っていきます。
糸を選べるところはあまりなく大変好評だそうです。
あとは藍染でハンカチを染める体験や、型染でハンカチ・巾着を染める体験もあります。
こんなにたくさんの体験が出来るスポットはあまりないので、気になった方は是非申し込んでみてくださいね。
-----------------------------------------------------------------------
4.「ふじや衣裳」で着物をレンタル
着物の着付けは「ふじや衣裳」でお願いしました!

西武鉄道「西武秩父駅」より徒歩8分、
秩父鉄道「御花畑駅」より徒歩5分と好立地にある着物レンタルショップ。
「ふじや衣裳」では皆さんの人生の節目に関わることができれば、とレンタルや記念撮影など色々なサービスをされています。
着物レンタルでは「女性着物プラン」3,000円(税別)の街歩きにぴったりなプランが大変人気です。
銘仙も選べるので気になる方はレンタルしてみてくださいね!
今回はおすすめプランの「袴姿プラン」8,000円(税別)をお願いし着付けをしていただきました!


こちらは着物のほんの一部。
着物は銘仙も多く袴との組み合わせを悩んでしまいますが、お店の方がアドバイスしてくださいますよ。
着物が決まれば2階へ移動し着付けです!
オプションでヘアセットもしていただけます。

店主の木﨑 祐子さんは『着物を着て残念な思いをしてほしくない。着物ならではの楽しい体験をしてほしいです。お客様がどこに行ったのかや、道行く先々で声をかけられた話などを聞くのがとても楽しみなんです。』と仰っていました。
ご自身も色んなお店へ行き、お客様におすすめされているそうです!
もし観光先やカフェなど迷っている場合は木﨑さんに尋ねてみてくださいね。
素敵なスポットを教えていただけますよ!
-----------------------------------------------------------------------
今回は埼玉県・秩父にある<ちちぶ銘仙館>にお邪魔しました!
秩父銘仙のデザインは、学校で「アール・デコ」や「アール・ヌーヴォー」といわれる装飾美術を学んだ学生が織元に原画を売りに行き、買い取られたものが採用されていました。
当時は最先端なデザインがとても人気でしたが、今でも「大正ロマン」や「昭和モダン」と言われ人気は衰えません。
着物レンタルショップにも「銘仙プラン」を取り扱うお店もあり、着用することが可能です。
色鮮やかな「銘仙」を着て、お出かけをしてみてはいかがでしょうか。
----------------------------------------
ちちぶ銘仙館
●住所:埼玉県秩父市熊木町28-1
●電話:0494-21-2112
●開館時間:9:00〜16:00(体験受付は15:00まで)
●休館日:年末年始(12月29日〜1月3日)
●入館料:一般 210円/小・中学生 100円
●HP:http://www.meisenkan.com/
----------------------------------------
ふじや衣裳
●住所:〒368-0043 埼玉県秩父市中町10-3
●電話:0494-23-3456
●営業時間:9:30~18:00
●定休日:第2・第3火曜日 / 水曜日
●HP:http://www.fujiyaisho.com/lp/kimono/
-----------------------------------------------------------------------
※データは2021年11月時点での情報です。
最新の情報は施設にお問い合わせください。
▼STAFF
モデル:窪内いくみ(アウグストゥス)
撮影:岩嵜一真
取材・文:キモノプラス編集部