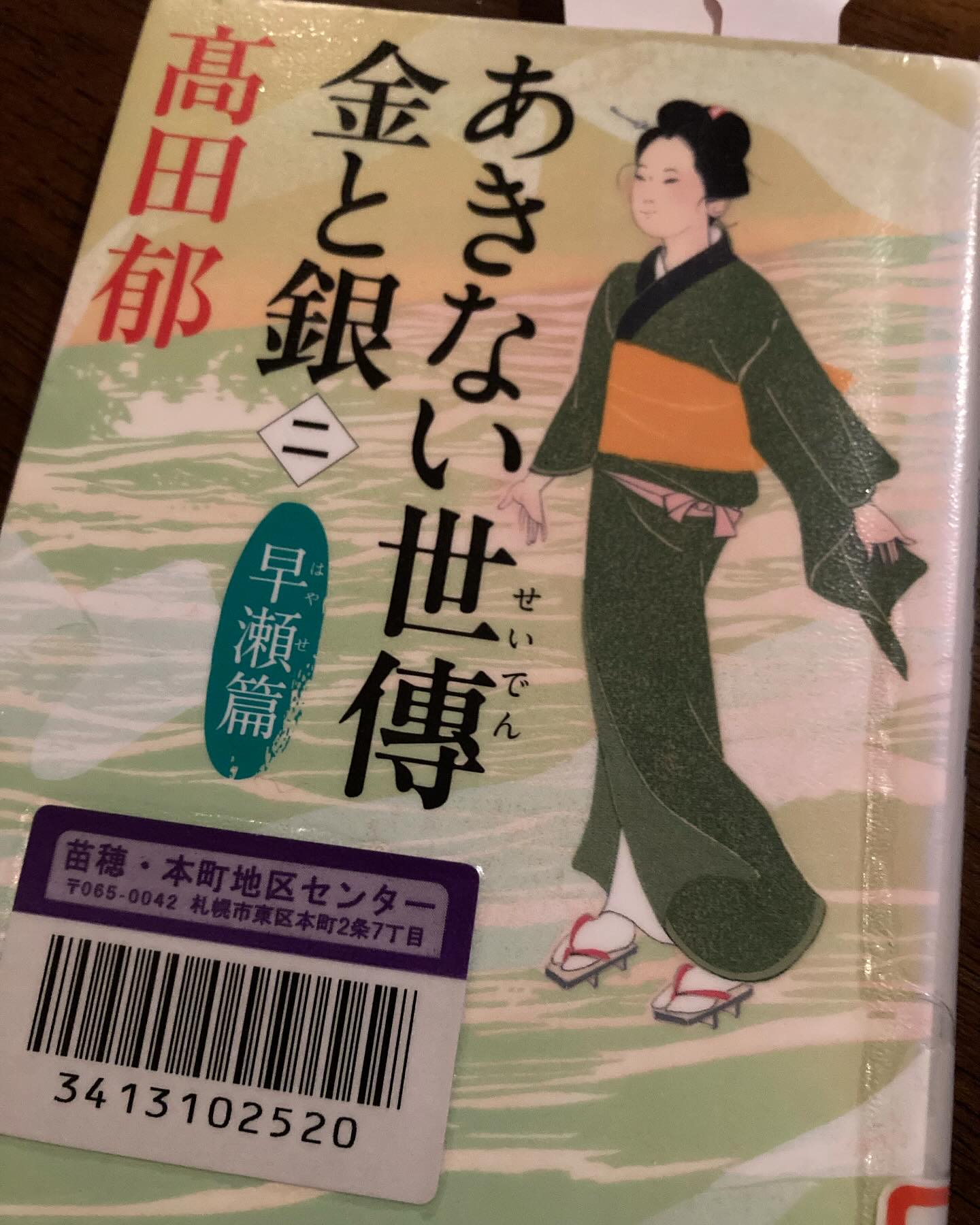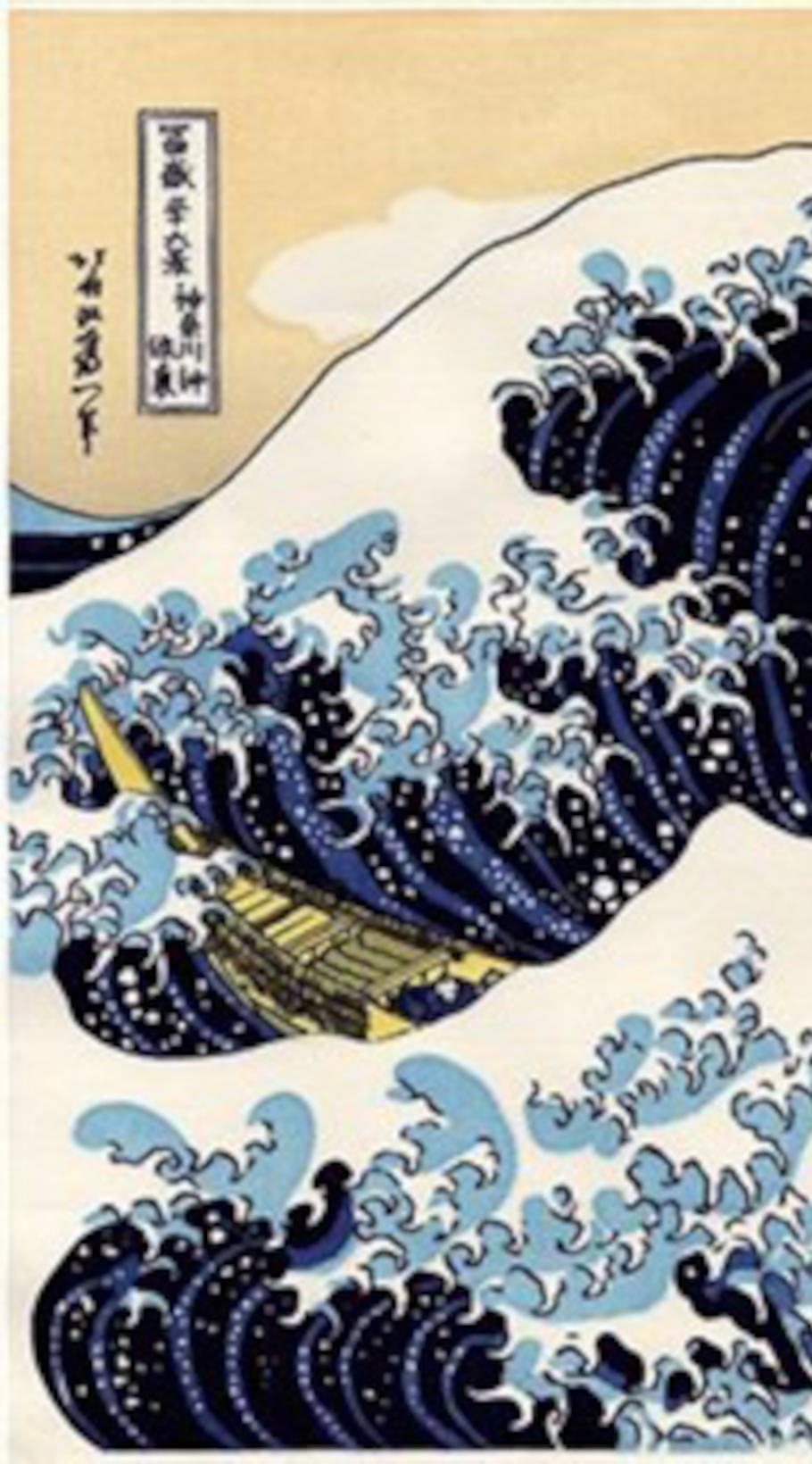【お茶会特集②】お茶室の造りって?よく見かけるあの名称は?
日本の伝統文化の1つ、「茶道」。
茶道には、おもてなしの精神やわびさびの心など、美しい魅力がたくさん。

知れば知るほど魅了されるお茶の世界。
このお茶会特集では、茶道初心者さんに向けて、お茶会に関する知識や情報・魅力をたっぷりお届けしていきます!
今回は、知っておくと便利なお茶室の構造、名称編です。
それでは、スタートです!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・待合(まちあい)

茶室に入る前に、客人が集まり亭主に呼ばれるのを待つ場所。
茶室には、露地(ろじ)と呼ばれる庭が付随されており、そこに設えられた待合を特に「腰掛待合(こしかけまちあい)」と言います。
・蹲踞(つくばい)

茶室(=神聖な場所)に入る前に身を清めるためのもの。
待合からお茶室に到達するまでの途中にあり、客人はこの蹲踞で手を洗って口をすすぎ、身を清めます。
やり方は、神社の参拝前の手水(ちょうず)と同じで
①右手で水をくみ、左手を清める
②左手に持ち替え、右手を清める
③右手に持ち替え、左手で水をうける
④左手に受けた水を口に運び、口を清める
⑤柄杓(ひしゃく)を立て、柄杓を清める
この流れになります。
・躙り口(にじりぐち)

茶室に付属する、お客様用の小さい出入口。
客人は、この躙り口からお茶室へと入ります。
どんなに身分が高い人でも、頭を下げなくては茶室に入ることができないことから、「茶室の中ではすべての人が平等」ということが示されています。
にじる(正座のまま少しずつ膝をつかって進む)ようにして入ることが名前の由来となっています。
・小間(こま)、広間(ひろま)

四畳半以下の小さな茶室を小間と呼び、四畳半以上の広いつくりの茶室を広間と呼びます。
亭主と客人の親密な関係をつくるため、安心感のあるコンパクトな茶室が誕生したと言われています。
・床の間(とこのま)

掛軸やお花を飾るところ。
掛軸やお花も茶道にとって欠かせない芸術です。
季節を表すだけでなく、同じ花には二度と会えないという一期一会の役割を果たしているお花。
派手に鮮やかに飾るのではなく、まるで自然の中に咲いているようなありのままの姿を表現するため、「投げ入れ」という様式で生けるのが原則とされています。
投げ入れ・・・頃合いに切った花を手で一度に花入れに入れる様式のこと。
・炉(ろ)

畳の下に備え付けられている小さな囲炉裏のこと。
ここに炭を入れて火をおこし、お湯を沸かすもので、この「炉」は11月~4月の寒い時期に使用します。
反対に、5月~10月の暖かい時期には、風炉(ふろ)と呼ばれるものを使用します。
こちらは、炉を閉じて畳の上に置いた風炉に炭を入れて火をおこし、お湯を沸かすものです。
お茶室は様々な構造で成り立っていますが、1つ1つに意味があります。
名称や意味を知ることで、より『茶の湯の精神』の理解がより深まります。
実際にお茶会に参加した際には、ぜひお茶室の構造にも目を向けてくださいね!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
お茶会特集、いかがだったでしょうか。
第2回は、お茶室の構造、名称編でした。
それでは、次回もお楽しみに!
お茶会特集トップはこちらから
https://www.kimono-plus.com/hashtag/434/ja-JP/2
撮影:岩嵜一真
撮影協力:茶瑠 BY 淡交社
着付け・モデル:猪尾雪乃
編集・文:キモノプラス編集部