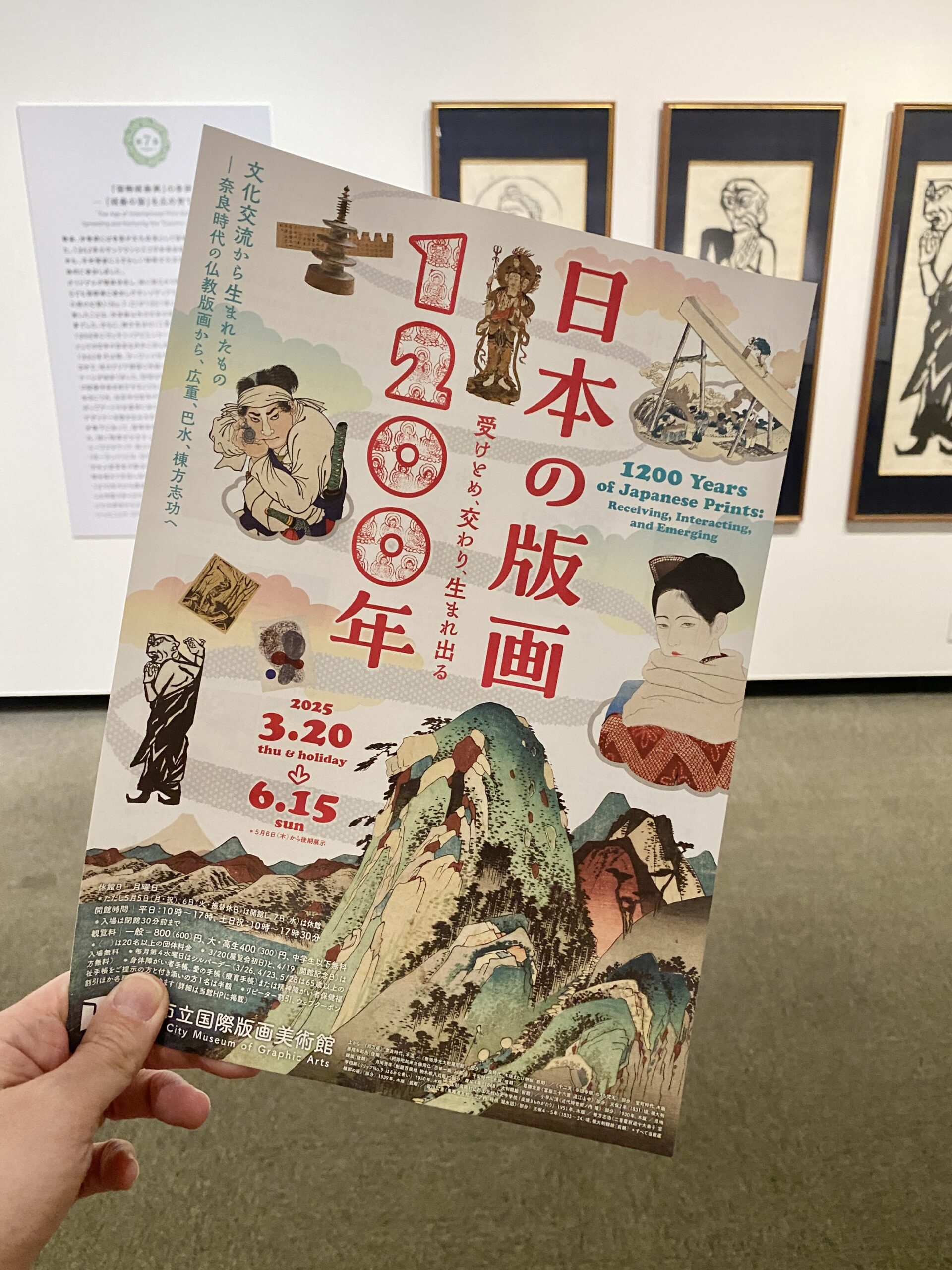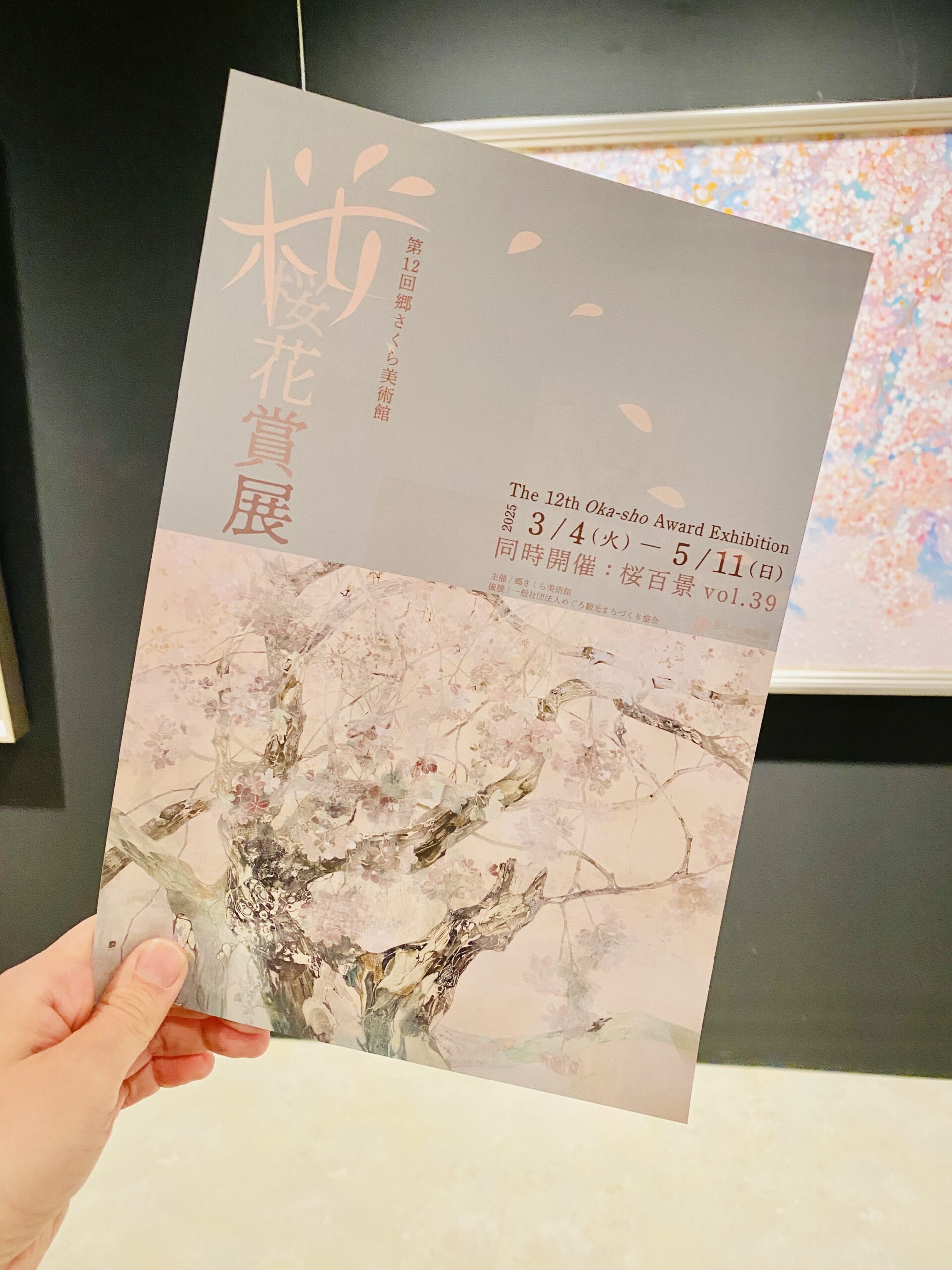【徳島県・本藍染矢野工場】体験して感じた藍染の奥深さ。

日本再発見の旅。〜藍染とは?本藍染矢野工場で学ぶ〜
かつて「阿波といえば藍、藍といえば阿波」と言われたほど、徳島県は藍の一大産地でした。
現在も伝統が引き継がれ、藍の栽培から藍染まで盛んに行われています。
今回 徳島県・藍住町にある<本藍染矢野工場>にお邪魔し「本藍染体験」をさせていただきました。
藍染商品を手に取ってみたりと知っている方も多いと思いますが、そもそも藍染とはどのような工程で染められているのかご存知ですか?
詳しくご紹介していきたいと思います!
【目次】
1.藍染とは?
2.<本藍染矢野工場>を訪問
3.「本藍染体験」を徹底リポート!
-----------------------------------------------------------------------
1.藍染とは?
藍染とは何の植物で、またどんな方法で染められているのか皆さんご存知ですか?
タデ科の蓼藍(たであい)という葉を染料として用いた染物です。

植物などの違いはありますが世界中で行われていた染色技法で、日本には奈良時代に中国から朝鮮半島を経て伝来したといわれています。
日本各地で藍が栽培されていましたが、徳島県では江戸中期以降どこも敵わないほど品質の良い藍が育てられており 今でも藍の一大産地です。
江戸時代になると藍が庶民にも広まり、衣類やのれん・寝具など身の回りのものに使われていました。
大正時代の中期までは国鉄や郵便局の制服に藍染の布が使用されていたそうで、日本人にとって馴染み深いものです。
藍染には「生葉染め(なまはぞめ)」と「建て染め(たてぞめ)」の2種類の染め方があります。
「生葉染め」とは藍の葉をすり潰し、出てきた汁を白い布などに染み込ませて酸化させ藍色に染める、という方法です。
最も古い染め方といわれています。
そして「建て染め」とは蒅(すくも)を微生物により発酵させることで水溶性の染料に変え、そこに布などを漬けて染める、という方法です。
◎蒅(すくも)とは乾燥させた藍の葉を細かく刻み、水を加え数ヶ月かけて発酵・熟成させた染料のことです。
そして模様や柄を表現する染色技法はたくさんあります。

今回は古代からある三種類の染色技法「三纈(さんけち)」をご紹介したいと思います。
「纐纈(こうけち)」
纐纈は絞り染めのことです。
生地を糸や紐で縛ったり生地を縫ったりし、その部分の生地が染まるのを防ぐ技法です。
「夾纈(きょうけち)」
夾纈は同じ文様を彫った2枚の板の間に生地を固く挟み、文様の部分に穴をあけて染料を注いで染め上げる技法です。
「臈纈(ろうけち)」
臈纈はろうけつ染めのことです。
布に溶かした蝋(ろう)で絵付けをし、染める技法です。
蝋の部分は染まらず残ります。
今回はこの臈纈の染色技法を使用し、藍染体験をさせていただきます。
-----------------------------------------------------------------------
2.<本藍染矢野工場>を訪問
今回<本藍染矢野工場>にお邪魔し、矢野藍秀(やの らんしゅう)先生にお話を伺いました!

<本藍染矢野工場>では「白花小上粉(しろばなこじょうこ)」という品種の藍を使用されています。
この白花小上粉の種は一般には販売されておらず、限られた農家さんしか栽培されていません。

(写真提供:本藍染矢野工場)
徳島県の藍住町という土地は山と太平洋と吉野川の三角州のど真ん中にあり、土は「真土(まつち)」という石のない良質な土壌のためとても良い藍が育つそうです。
藍は食用として食べることができます。
生のままサラダとして、片面に衣をつけ天ぷらにして食べたり。
そしてさらに凄いのは、胃腸など消化器系の薬として用いられていたという歴史があることです。
そしてこちらでは「天然灰汁発酵建て(てんねんあくはっこうだて)」という方法で本藍染を行われています。
布を染められる状態にするには、ものすごく時間も労力もかかる大変な作業です。
「徳島で育てた阿波藍で蒅(すくも)を作り、灰汁発酵建て(あくはっこうだて)といわれる藍甕(あいがめ)を使って建てる」これが基本だそうです。
「徳島で育てた阿波藍で蒅(すくも)を作り、灰汁発酵建て(あくはっこうだて)の技法で、藍甕(あいがめ)を使って建てる」これが基本だそうです。
蒅が一杯入ったタライがいくつもありました。

蒅を丸めたものを藍玉(あいだま)と言います。
こちらが藍甕です。

徳島の伝統工芸品である大谷焼で作られており、約280リットル入るそうで部屋の中には床に埋められた状態で並びます。

蒅だけで色は出ないので染色できません。
藍甕の中に、蒅・石灰・木灰の灰汁・日本酒などを入れ発酵させ発酵液を作ります。
出来上がるまで毎日、攪拌(かくはん)します。
蒅はタライ1個分入っているため底から混ぜるのにとても体力を使います。
矢野先生は軽く混ぜられているように見えましたが、腕力がないと全体が混ざらないそうです。

真ん中に浮かんでいるのは「藍の華」です。

(写真提供:本藍染矢野工場)
毎日藍の状態を見ながら混ぜることが大切だそうです。
生き物と一緒なので健康状態を色や大きさ・匂い(発酵臭)で確認されています。

パッと見ると黒く見えますが、攪拌している時などよく見ると紫や黄・深い緑などいろんな色に見えてとても綺麗です。
藍色は日本を代表する色として「ジャパンブルー」と呼ばれています。
-----------------------------------------------------------------------
3.「本藍染体験」を徹底リポート!
今回<本藍染矢野工場>で「ろうけつ染め」を用いた染め体験をさせていただきました!
大きめのハンカチ、バンダナくらいの布を染めていきます。
では早速、レポートしていきたいと思います!
①布に蝋で絵付けをする
まずは布にデザインを描いていきます。
描いた部分は染まらず白いまま残ります。
これが蝋(ろう)を溶かしたもので、筆に含ませ描いていきます。

含ませすぎるとポタポタと落ちてしまうので気をつけながら、、
でも含ませるのが少なすぎると表面だけに付き白く固まってしまいます。
この状態だと裏から染まってしまうので、下に敷いている新聞が透けるように描くのがポイントです!
布の糸に浸透させるイメージです。

好きなデザインを、と言われると困るほど絵心がないので会社のロゴを描きました。(スペルが1つ抜けているのは秘密です、、)
②染めていく
藍甕(あいがめ)は深さ1メートル程あるので物を落とさないように気をつけましょう!
布を持ったまま発酵液に漬けるとその部分が染まらないので、同じ長さの棒を付けてもらい、利き手に手袋をして準備は完了です。
それでは藍甕に浸け、染めていきます!
始めはうまく沈んでいかないので、ゆーっくり左右に揺らしながら浸けていきます。

布が全部浸かったらそのまま1分〜1分半待機です。
発酵液はひんやりと冷たく、発酵臭が少しありますがくさい匂いではありません。
1分程浸けて上げてみるとこの様な色に。
藍色というよりは黄味のある茶色のような色です。

そして藍甕から出した状態で1分ほど待機です。
この時、空気に触れることで酸化し色が定着していきます。
「出してすぐの色」と「1分経った時の色」は、酸化という工程を経て変わっています。
この工程がとても大事で、繰り返すことで層のように染まっていきます。
そしてまた発酵液に浸けます。
これを繰り返すのですが、回数は染めたい色により異なります。
明るめの藍色に染めたい人は少なめに。
逆に濃い藍色に染めたい人は多めに。
私は「褐色(かちいろ)」と言われる濃い藍色に染めたかったので多めに、トータル10回繰り返します。
引き上げるたびに色が変わっていき、徐々に染まっていくのが目に見えて分かります。

そしてこちらが10回繰り返した後のハンカチです。

全然色が違いますよね!
イメージしていた色に染まっていそうです!
③蝋を落とす
次は蝋を落とすという工程ですが、どのように落とすと思いますか?
冷えて固まった蝋を溶かすには「熱いもの」です。
熱湯をかけて蝋を洗い流します。

表と裏の両面に熱湯をかけ、蝋が流れてしまえば大丈夫。
綺麗にアイロンをかけていただき完成です!!

どうでしょうか?
私がイメージする藍色・褐色で、とっても良い色に染まりました。
蝋で書いた部分で少し染まっているところがありますが、この部分は裏地まで蝋が染み込んでいなかった箇所ということになります。
これはこれで味があり良いですね♪
糸の1本1本までしっかりと染まり、生地が少し硬くしっかりした様に感じます。

藍甕の前に座り、布を漬けたり出したり。
少し腕がだるくなりますが、出すたびに色味が変わっていく様子を観察するのはとても楽しかったです!
一言で「藍色」と言ってもたくさん種類があり奥がとても深いです。
染める回数を調整し、自分だけの色を表現してみませんか?
<本藍染矢野工場>ではお子さんも体験していただけます。
特に蝋で絵を描く時には夢中になって作業する子が多いそうで、貴重な体験になること間違いなしです!
皆さんにもぜひ体験していただきたいです。
-----------------------------------------------------------------------
今回は「藍染について」と「本藍染体験」をまとめてみましたが いかがでしたか?
藍で染められたハンカチはUVカット効果があるので首に巻くと日焼け対策になります。
染色に使ってよし、食べてもよし、薬にもなる「藍」。
スーパー植物ですね!
先人たちから受け継いだ技術や知恵を継承し、それをまた繋げていく。
素晴らしい体験をさせていただき、タイトル通り「日本再発見の旅。」となりました。
少しでも藍に興味を持っていただけたら嬉しいです!
なかなか藍を食べるというのは難しいですが、藍染の商品を見かけた時は手に取って見てみてくださいね。
---------------------------------------
本藍染矢野工場
●住所:徳島県板野郡藍住町矢上字江ノ口25-1
●電話:088-692-8584
●HP:http://yanokozyo.com/
-----------------------------------------------------------------------
※データは2021年7月時点での情報です。
最新の情報はスポットにお問い合わせください。
撮影:岩嵜一真
取材・文:キモノプラス編集部