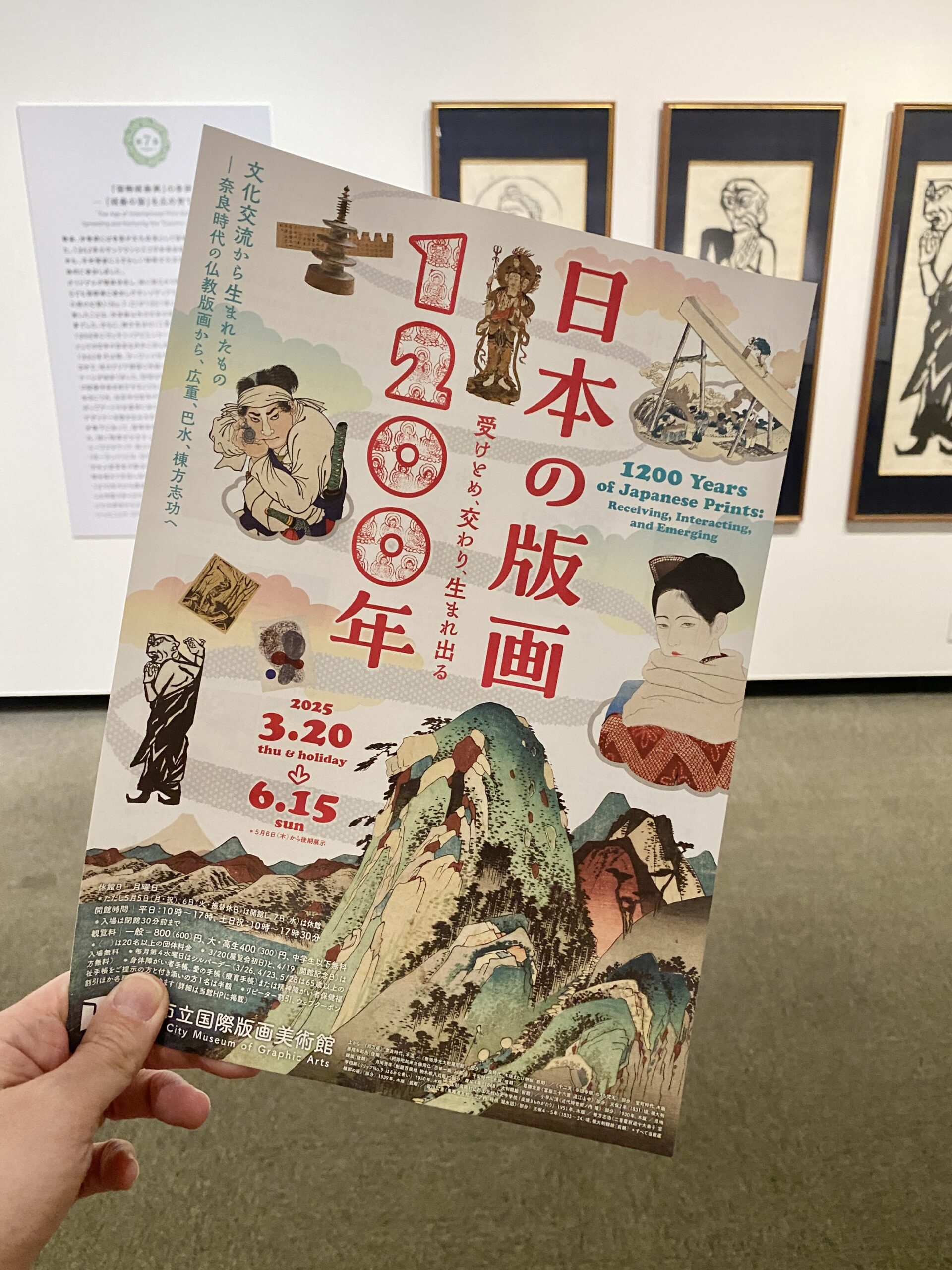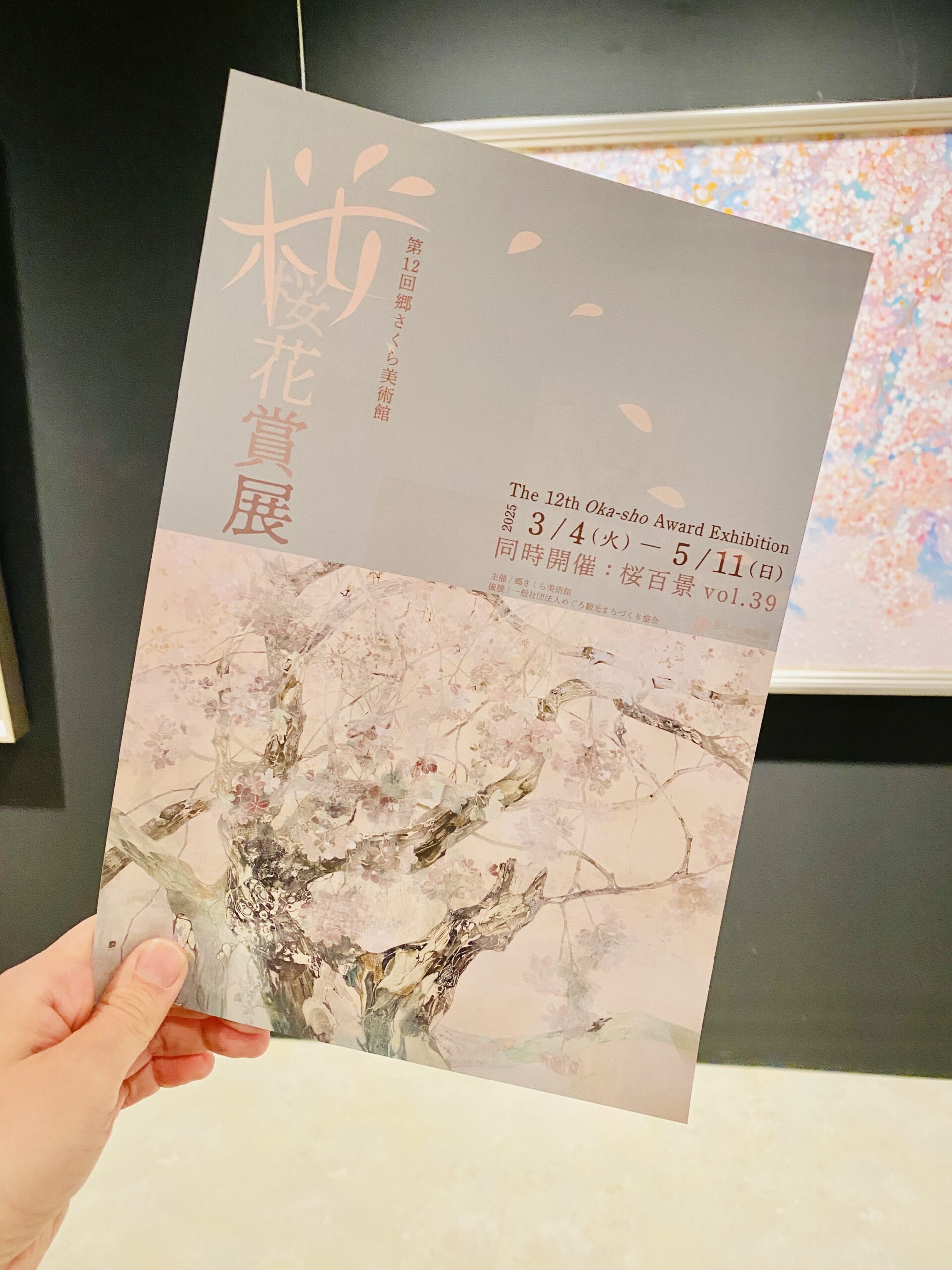[着物でお出かけ] 型染〜日本の美
 今回は、東京渋谷区にある「文化学園服飾博物館」へ型染のお勉強へ伺いました。
今回は、東京渋谷区にある「文化学園服飾博物館」へ型染のお勉強へ伺いました。
型染とは、紙や木の型を使って布に文様を染める技法です。
主に、防染、捺染、注染がありますが、その技法についても映像などで分かりやすく展示してありますので、技法の説明については省略します。 エントランスに展示してあったお着物
エントランスに展示してあったお着物
(残念ながら館内は撮影できません)
江戸時代から現代までの型染の歴史が4つの章で構成される展示となっています。
◆第一章は江戸時代
型染は鎌倉時代から始まり、江戸中期頃までは裃に代表される武士の公服に用いられていましたが、江戸時代後期になると、木綿に型染した浴衣が庶民にも着られるようになったそうです。当時の型紙や小紋帳のほか、染色職人の様子や庶民が浴衣を日常着として愛用していた様子が伺える絵画なども展示されています。
◆第二章は明治時代
新しい時代になり海外から洋服も入ってきましたが、庶民の日常着は着物。伝統技術を引き継ぎながら、複数の型を使って複雑な文様を染めたり、刺繍や友禅を組み合わせたり、より精緻な技術が高められた時代です。柄の表現も豊かで、役目を終えた蚕の成虫と枯れ落ちた桑の葉、その上に白の絹糸が描かれた秋の着物には、とても儚さを感じました。◆第三章は大正時代と昭和初期
化学染料を使用したり捺染という新技法が開発されるなど、今までの防染を基本とする型染から一変、色鮮やかな型染めができるようになり、庶民の女性たちの着物も華やかになりました。男性の着物は縞や無地が多めでしたが、タイプライターや高層ビルなど、世相を反映した柄の襦袢が流行り、見えないおしゃれを楽しんでいたようです。素敵ですね。
◆第四章は現代
戦後は着物を日常着として着る方は少なくなり、今まで衣生活を支えてきた型染は生産量も減少していますが、型染作家は、伝統工芸士として更なる技術や技法を磨き、これを次世代に繋げる努力をしています。 現代の型染浴衣
現代の型染浴衣
冷房で冷えすぎないようにお着物でのお出かけがおすすめです。私は型染の浴衣で見学してきました。 ーーーーーー
ーーーーーー
型染〜日本の美
開催期間 2022/6/15(水)〜8/4(木)
文化学園服飾博物館
東京都渋谷区代々木3-22-7
新宿文化クイントビル1階
都営大江戸線 「新宿駅」徒歩4分
https://museum.bunka.ac.jp/